
メンバー日記
 叔父のもと邦楽の修行を続けていた久は、帝大の学生となって東京に住む兄弥太郎の助言に従って京都を離れ、東京音楽学校への入学準備を始めるべく上京する。そのとき彼女は15歳であった。しかし、己の人生の岐路に立っていることを充分に自覚していたに違いない。
叔父のもと邦楽の修行を続けていた久は、帝大の学生となって東京に住む兄弥太郎の助言に従って京都を離れ、東京音楽学校への入学準備を始めるべく上京する。そのとき彼女は15歳であった。しかし、己の人生の岐路に立っていることを充分に自覚していたに違いない。
上京して間もなく兄に連れられて見に行った浅草の活動写真に、一人のみじめな乞食(こじき)の姿が登場した。それを見た久の胸中には突如として熱い感情が込み上げ、激しい不安が自分を揺さぶるのを感じた。これから自分はピアノという全く自分にとって未知の世界に挑もうとしている。しかし、ここで失敗をしても、もう叔父のもと、邦楽の世界に戻ることは許されなかった。そうなったら自分もまた、あの活動写真のように落ちぶれ、路上に座して往きずりの人々の慈悲にすがることになるだろうか….
文字通り背水の陣をしいて、ともかくも久は音楽学校の予科へ入学を許されたが、入学はしたものの、彼女の指導教官たちは久の将来については全く懐疑的であった。何人もの教師が次々に久を教えてみたあげく、彼女は「退学をした方がよいのではないか」とまで勧告されたのである。そのとき久は教官の前にひれ伏して泣き、「明日まで待って下さい」と頼み込んだ。そしてその足で医者を尋ねて健康診断をして貰い、どこも悪いところはないと知ると、翌日学校の教官に「とにかく退学は致しません」ときっぱりと宣言した。そして、その夜から凄ましい練習を開始したのであった。
それは文字通り、火を吹くような激しい練習であった。無理もない。15歳になってから本格的に始めたのである。
 真冬の夜、火鉢さえも入っていない教室に残って、彼女はピアノをさらった。床から伝わる冷気が腿(もも)の感覚をしびれさせ、指先を氷のように凍(こご)えさせても、彼女の練習は深夜に及んだ。
真冬の夜、火鉢さえも入っていない教室に残って、彼女はピアノをさらった。床から伝わる冷気が腿(もも)の感覚をしびれさせ、指先を氷のように凍(こご)えさせても、彼女の練習は深夜に及んだ。
或る夜、明りはついているのにしんと静まり返った教室に不審を抱いた教官が入って行ってみると、赤い帯を締めた久がピアノの鍵盤の上に突伏した。驚いた教官が何事が起こったのかと走り寄ると、久は眼いっぱいに涙をこらえて顔を上げた。ずっと泣いていた様子であった。「こうして一心に勉強はしておりますけれど、先のことをふと考えますと遠くて、とても手が届きそうには思えなくて….」と放心したように久はつぶやくのであった。
自宅にピアノが入り、好きなだけ練習ができる状態になると、彼女はしばしば夜を徹してさらい、ピアノに寄りかかって仮眠し、そのまま登校するといったなりふり構わぬ様子もみせるようになった。朝食はおにぎりを用意して貰っておいて、登校中に食べながら学校に向かうのである。友人がふと見ると、髪はくしゃくしゃ、口の横にはごはん粒がついたままで、そんな風体のうら若き娘が、不自由な足を引きずって教室に急ぐ姿は、さぞ異様な光景であったことだろうか。そして、そういった極端な無理がたたったに違いない。久は間もなく、肋膜(ろくまく)を患うことになる。しかし、久は強靭な精神力で肋膜炎を克服することになる。
久は明治39年(1906年)、東京音楽学校本科器楽部を優秀な成績で卒業、更に研究科に進む。更に師範の免状を得て、翌年からは母校で助手を務め始める。
15歳で邦楽を見限って上京し、背水の陣をしいてピアノに立ち向かった久は、それから10年もたたずにして日本にただ一つしかない洋楽の専門学校の教官となったのである。しかもそのとき久のピアニストとしての「名声・人気」は既に他に匹敵する者のない程際立っていた。
 洋楽における欧米留学生第一号であった恩師の幸田延を例にとるまでもなく、当時いささかでもピアノで名をあげた人々の大部分は、ヨーロッパやアメリカの土を踏んだことのある者ばかりで、しかも当然のことながら資産家や特権階級の子女ばかりに限られていた。しかし久は、日本で生まれ育ってそこで音楽教育を受け一人前になった最初のピアニストであった。いわば、純国産ピアニスト第一号である。しかも名流の出どころか、むしろ貧しい出身であった。
洋楽における欧米留学生第一号であった恩師の幸田延を例にとるまでもなく、当時いささかでもピアノで名をあげた人々の大部分は、ヨーロッパやアメリカの土を踏んだことのある者ばかりで、しかも当然のことながら資産家や特権階級の子女ばかりに限られていた。しかし久は、日本で生まれ育ってそこで音楽教育を受け一人前になった最初のピアニストであった。いわば、純国産ピアニスト第一号である。しかも名流の出どころか、むしろ貧しい出身であった。
足が不自由であるとはいえ、久は細おもてで色白の小柄な顔立ちであったから、彼女を美人と心密かに憧れて、演奏会にやってくる帝大の学生たちも多かった。その美人がピアノの前に座るとしばしば目を閉じて、「あたかも作品に自分自身の魂を乗り移らせようとするかのように」神経を集中する。そして一旦演奏が始まると色白の頬から耳たぶにかけてさっと紅(くれない)に染まり、そこにやがて汗が一すじ二すじ艶(つや)やかに流れ、華奢(きゃしゃ)なうなじに後れ毛がべっとりとまといつく。身体じゅうを震わせて満心の力を込めてピアノを「ぶっ叩く」と、着物は乱れ、帯は緩み、花簪(かんざし)はステージのどこかにふっ飛んでしまう….そう、久はピアノと闘っていたのである。 ところで、この久の演奏そのものについてであるが、文献から想像するところよると、その特徴は、一にも二にも「激しさ」であり、髪が乱れ簪がふっ飛んでしまうほど「身体を震わせて動かしたり」、更にはピアノを「ぶっ叩く」という点にある。彼女の演奏について、抒情的、優雅、あるいは弱音の美などを讃えた言葉は皆無である。
ところで、この久の演奏そのものについてであるが、文献から想像するところよると、その特徴は、一にも二にも「激しさ」であり、髪が乱れ簪がふっ飛んでしまうほど「身体を震わせて動かしたり」、更にはピアノを「ぶっ叩く」という点にある。彼女の演奏について、抒情的、優雅、あるいは弱音の美などを讃えた言葉は皆無である。
この殊にピアノを弾くと言うときに使用される「ピアノを叩く」という言葉、これこそ明治以来百数十年にわたって日本のピアノ演奏を支配してきた或(あ)る精神をシンボリックに表した言葉であるといえよう。
久野久はむしろ、その師の幸田延にしろ、幼い頃から西洋音楽に親しんでいたわけではなく、ピアノを好きで始めたというわけでもない。彼女たちが幼少の頃影響を受けたのはまず邦楽であり、そして筝(そう)や三味線の修行を通じて身に付けた邦楽の世界のルールやマナーであった。
幸田延は10代の終わりから20代の半ばまでという、人生で一番多感な時代を欧米で過ごしているのだが、そんな延さえも「三つ子の魂百まで」の言葉通り、邦楽には一生を通じて深い親しみを抱き続けていた。当時の東京音楽学校の使命の一つが「西洋音楽と邦楽の新しい融合」にあったためもあるかと思われるが、延はよく弟子たちに「呼吸、間のとり方を邦楽に学べ」という助言をした。
教師となった久はその性格からいっても、尋常ならざる熱心さで生徒たちを教えたことは想像にかたくない。決して妥協をせず、適当にお茶を濁すといったやり方は彼女の性格に反していたから、それは生徒たちにとってみれば、この上なく厳しい先生であった。
(その4に続く)
 おゆみ
おゆみ
40代にして音楽学者をめざして、音大の楽理科に進学するために勉強中。来年1月の発表会に向けてショパンの「ポロネーズ第1番」を演奏するため、必死に練習に励みながら、日本における西洋音楽の黎明期の研究に情熱を注いでいる。








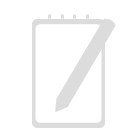
Leave a reply