
メンバー日記
 途中上海に立ち寄ってリサイタルを行い、久がベルリンに到着したのは、7月12日のことだった。久は36歳にして初めてヨーロッパに降り立ったわけになる。
途中上海に立ち寄ってリサイタルを行い、久がベルリンに到着したのは、7月12日のことだった。久は36歳にして初めてヨーロッパに降り立ったわけになる。
ベルリンでは日本の代理大使が、「日本の最も高名なる女流ピアニスト」を歓迎すべく待機していた。彼女はその公邸の賓客(ひんきゃく)となるのだが、間もなく代理大使たちはこの天才女流芸術家の「奇行」に肝をつぶすことになる。
音を立てながらスープをすするなどということは朝飯前、銀行の待合室で腹巻の財布を取り出すといって突然帯を解き始める、振袖姿に素足にゴム草履といったいでたちで盛り場を歩き廻る。36歳の今日まで、日本の官立学校の教授として人気名声ナンバーワンの地位にあった彼女に対して、渡欧の際に欧米でのエチケットやマナーを伝授する者など一人もいなかったのも思えば不幸なことであった。
更に当時の日本人としても小柄な久が和服を着て、「不自由な足の膝に片手を添えつつ波のように上下させながら」ベルリンの街を歩くと、道行く人々は立ち止まり好奇心に満ちた眼差しで彼女を見つめた。指差して露骨に嘲笑する若者もいる。
オペラ見物では、きらびらかな夜会服を纏った背の高いドイツ人の紳士・淑女たちのまるで人間の森のようにそそり立つ中を、黄色い肌の眼の細い貧弱な日本人女性が、黒っぽい和服を着こんでまるで森の中で道に迷った子ねずみのようにチロチロと歩く。その久が、シャンデリアの輝く壮麗な白大理石の階段を波をうたたせながらよちよちと昇っていくと、紳士・淑女たちの視線は一斉にその姿に釘づけとなった。
久に付き添って案内する代理大使以下、当時の日本を精一杯代表して頑張っていた人々にとっては、それは耐え難いいっときであった。彼らは自らもヨーロッパ人であるかの如く振る舞い、服装も整えてマナーにも気を配っていた。それなのに、久は頑として洋装になろうとはしないで、目立つ「日本服」で通そうとする。足の悪く背の低い久には、実際のところ洋装は全く似合わないものでもあったのだが、必死の努力を傾けてヨーロッパ社交界に仲間入りしようとしていた代理大使の眼には、久の和服は「国辱」とさえ映った。
代理大使は、久の滞在僅か数日にして悲鳴をあげる。そして久はほとんど追い出されるかのように、公邸から締め出されてしまったのである。 しかし久は、そんなことではくじけなかった。ベルリンで一度演奏会をしなければ、とちょうど彼の地に滞在していた音楽評論家の兼常清佐(かねつね・きよすけ(1885-1957))に語る。
しかし久は、そんなことではくじけなかった。ベルリンで一度演奏会をしなければ、とちょうど彼の地に滞在していた音楽評論家の兼常清佐(かねつね・きよすけ(1885-1957))に語る。
「それは翼なしに空を飛ぼうとするようなもんですよ、クノさん!もうベルリンを見たからいいでしょう。明日東京にお帰りなさい。ベルリンは決してあなたのいる処ではない。」(兼常清佐『英雄クノ・ヒサコ』)
この兼常の「思い出」は1950年代、つまり日本のクラシック音楽への理解もかなり向上し、久の悲観的役割もようやく明確になった時期に、自らの音楽評論家としての見識の「アリバイ」を意識して書かれた感じもあって、必ずしも言葉通りには受け取れないところがあるが、いずれにしても久は無邪気にこう答えたとされる。「ベルリンがいけなかったからウィーンに行きましょうか!ウィーンなら私の芸術を分かってくれるでしょうか。」
ベルリンでは演奏会をするどころか、久は不運続きであった。代理大使の公邸を出てから見つけたペンションは高級であったが、口喧(やかま)しい老婆がいてことごとく彼女に辛く当たった(とドイツ語のできない久は思った)。洋食が苦手で、殊(こと)に久は肉料理一切がのどを通らなくなってしまった。そのためペンションでは特別許可を貰(もら)って漬物とご飯を作りそればかり食べて過ごすといった状態であった。こうした食生活は、その後バーデンで亡くなるまで続けられる。
ドイツ語が喋れない、現地の食物がのどを通らない、生活習慣に馴染めない、そんな久にドイツ人の友人もできようがなく、また日本の音楽界では「天才音楽家」であっても、異郷に住む日本人たちの間では単なる奇人変人の類にすぎない。久はここでも孤独だった。しかし、彼女にとってそれ以上に辛かったことは、また指を痛めてしまったことである。ピアノが弾けない、これからヨーロッパを制覇しなければならないというのに….。
苛立つ思いをこらえて、久はベルリンでのコンサートに通い始めた。
ザウワー、ダンベール、フリードマン、フィッシャー、ケンプ、シュナーベル、ペトリ、クロイツァー、ブゾーニ….。私は今、彼女が直(じか)に耳にすることができたこれらの巨匠たちの名前を見るだけで、昂奮(こうふん)に胸がときめく。これらの顔ぶれは、あの19世紀から20世紀にかけてのピアノの黄金時代を飾る、文字通り歴史的ピアニストばかりなのであるから。
久は演奏会のチケットを買い、そのプログラムを調べると、すぐに楽譜を買ってきて勉強してみた。痛い指をかばいながら、「丁度学問の講義の下調べのように」楽譜を読み、演奏会にはその楽譜を携(たずさ)えて行く。そして、その中に様々な印象を書き込んでいくのであった。
こうやって巨匠たちの演奏ぶりを身近に観察して、久が強い衝撃を受けたのは当然のことであった。中でも彼女を驚かせたことは、それらの巨匠たちがみな久の想像もしていなかったような繊細で濃(こま)やかなやり方で、ペダルを使用しているということであった。それまでの久にとって、ピアノのペダルとは大きな音を響かせてたり、或いは小さく弱い音にするために踏むものとしての存在しかなかったのである。
このピアノのペダルが音量の大小を作るためのものだという巨大な誤解は、実は今日の日本のピアノ教育の場でも未(いま)だ根強く見られる。
あまり専門的になるのを避けてごく簡単に構造的な説明をすると、右側のダンパーペダルは弦の振動を抑えるフェルトを弦から遠ざける機能を持ち、その結果、音は開放弦として豊かに響き続ける一方で、様々な音が響きの中で混ざり合う(時には濁る)。また、左側のソフトペダルは、例えば、中音域以上では一音につき3本あるピアノの弦の2本だけを叩くよう、ハンマーを移動させる機能を持ち、結果としては音も小さくなるが、何よりも音質がかそけて弱々しく変わる。いずれにせよ大切なことは、二つのペダルとも結果として音量の大小ももたらすが、その本来の機能は、このようなピアノ自体の構造的な打弦方法の変化を導き、指による操作と組み合わせることで意図する音色を作り上げるためにある。極端な例を挙げれば、右のダンパーペダルを踏みながら、豊かなピアニッシモを弾き、左のソフトペダルを使いつつ、くぐもってやせこけたフォルティッシモを作ることも可能なのである。
 従ってこのペダルの使用法の発見が、久にとっていかに衝撃的なものであったか想像に難くない。彼女は要するにそれまで最も基本的なピアノの構造自体を知らないまま、文字通り血の滲(にじ)む、しかし頓珍漢(とんちんかん)な努力を重ねてきたことになるのであった。
従ってこのペダルの使用法の発見が、久にとっていかに衝撃的なものであったか想像に難くない。彼女は要するにそれまで最も基本的なピアノの構造自体を知らないまま、文字通り血の滲(にじ)む、しかし頓珍漢(とんちんかん)な努力を重ねてきたことになるのであった。
久自身の手記に従えば、このような久のショックを集約したかたちとなったのが、当時28歳でデヴューしたばかりのワルター・ギーゼキング(1895-1956)との出逢いであった。ギーゼキングの演奏には、匂(にお)いたつような高貴な輝きがあった。なんという柔らかな、馥郁(ふくいく)たる音色、霞のヴェールがかかったようなレガート、そして、嗚呼、なんと幻想的なピアニッシモ….。
これは、ギーゼキングが晩年の1951年に録音した、ベートーヴェンの「月光ソナタ」の第1楽章を拝聴すればお分かり頂けるだろう。
https://www.youtube.com/watch?v=4QbmCMLMit0E
今まで髪をふり乱してキイをぶっ叩くことばはりが情熱的な演奏である、とそこに全力をあげていた久が、ここで突如としてピアニッシモの絶妙な美しさに目を見開かれる。ピアノという楽器がそもそも「ピアノ」を呼ばれる所以(ゆえん)であるその弱音の魅力、その多彩さに目覚めたのである。
久はギーゼキングの演奏に熱中し、その演奏会に7・8回ほども通いつめる。そしてその奏法が、前述の巨匠たちとも全く違った「非常に新しい弾き方で」、その著しい特徴は左のソフトペダルをほとんど左足を後ろに引く隙もないほど頻繁に使用している点にあると克明に観察した(久の手記『芸術の苦しみ』)。
大正13年(1924年)の9月、久はコンサート通い以外はすることもなく不愉快なことも多かったベルリン滞在を打ち切って、ウィーンに移る。ベルリンで聴いた感銘を受けた老大家、エミール・フォン・ザウワー教授(1862-1942)がウィーン郊外の温泉地バーデンに住んでいると聞き、是非その教えを貰いたいと願ったからであった。「ザウワー教授は大変な偉さです。伯林(ベルリン)で五十回くらいピアノを聴いた中で最も偉いのです。」と、久は音楽評論家の牛山充(1884-1963)に宛てて書いている。
ザウワーはリストの高弟であった人で、私はYou Tubeでショパンの「幻想即興曲」を聴いたことがあるが、実に知的で繊細な音の持ち主で、高音域を処理するときは真珠の珠が天から転がり落ちるような、美しい音楽を奏でるピアニストである。久はザウワー教授を追ってバーデンの旅館に移り住み始める。
 バーデンはウィーン郊外25キロメートルの地点にあって、かつてはオーストリア皇帝一族の夏の保養地として知られていた。現在でも人口は25000程にすぎないが、最晩年のモーツァルトが美しい合唱曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を作曲及び初演し、べートーヴェンが第9交響曲と荘厳ミサ曲を作曲した地として有名であるが(べートーヴェンハウスもある)、クアパルクと呼ばれる広大な公園を中心に、野外音楽堂、カフェなどが点在する美しい街である。
バーデンはウィーン郊外25キロメートルの地点にあって、かつてはオーストリア皇帝一族の夏の保養地として知られていた。現在でも人口は25000程にすぎないが、最晩年のモーツァルトが美しい合唱曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を作曲及び初演し、べートーヴェンが第9交響曲と荘厳ミサ曲を作曲した地として有名であるが(べートーヴェンハウスもある)、クアパルクと呼ばれる広大な公園を中心に、野外音楽堂、カフェなどが点在する美しい街である。
ここの温泉は主として硫黄泉で、リューマチ、神経痛、筋肉痛に良く効く。手の故障に絶えず悩まされていた久には理想的な土地であったかも知れない。しかし、季節外れのバーデンは、一日中静まり返って人影もなく寂しい。夏には開催されるコンサートは今は無く、聞こえてくるのはただの森のざわめきばかりである。そんな忘れ去られたような環境の中で、久は虚しく時を過ごして行く。
https://www.youtube.com/watch?v=4lPggvToNZU
冬も間近に迫った頃、久は待望のザウワー教授について会えることとなった。
「ああ大正十三年十一月廿五日、この日は私にとって一生忘れることの出来ない吉日です。即ちこの日私はザウワー教授の御宅を初めてお訪ねして親しく御眼にかかる光栄に接することが出来たからです。」(兼常清佐宛の葉書)
久はザウワーの前で最も得意とするベートーヴェンの「月光」を弾き、ザウワーはブラヴォー・ブラヴォーと二度言って、その演奏を温かく迎えた。そして、「日本人が斯(か)くまで正確にまた芸術的に音楽を理解するとは今日まで思ってみなかった。」と賞賛した。
久の狂喜はいかばかりであったことか。彼女はザウワーの一挙手一投足がすべて彼女への讃辞につながる特別なことであるかのように受け止め、7回も握手をして下さった、とか、来年2月以降ならバーデンに戻っているからレッスンをしてあげてもよいと三度も繰り返して言って下さったとか、その昂奮ぶりを日本の知人たちに書き送る。そして、「私は来年(大正14年)四月にウヰンで独奏会をやる勇気をやつと出してゐます。」とも付け加えているのである。
ウィーンの次はベルリン、そしてパリ、ロンドン、ローマ….。そこでの大成功、輝かしい栄誉を背に、「日本へは八月初めに着くでせう。」と彼女は牛山に書く。と同時に彼女は日本に居ても一人では演奏して廻れないのに、私のやうな(身体の不自由な)者が外国で此五ケ所を廻つたり、それだけの勉強をしたならば体はもうへたばつてしまひます。ー音楽の知らぬ人も言ひます。『独(ドイツ)より以上だ。オーストリーの音楽は。』と。だからウヰンで私がやつたら十分でせう。(第一体がつづかないから)」と、気の弱さも見せている。(12月22日付)
しかしながら、このザウワーの讃辞は、遠い極東の異国から来たか弱い女性に対する、思いやりのこもった社交辞令の一種に他ならなかった。ザウワーは1879年から2年間、モスクワ音楽院でアントン・ルービンシュタインに学び、いわば久の奏法とは対極にある、ヴェルヴェットのような滑らかなタッチと洗練されたピアニズムの持ち主であった。彼はまた、激情の奔流に身を任せて「情熱的な演奏をするよりも、バランスのとれたスタイルとデリケートで知的な感性の表現に重きを置く詩人だった。そのザウワーが久の演奏を本気で絶賛する訳がない。
この頃、すでに久の生活はベルリン時代と違って窮乏に瀕していた。
日本を発つとき久は、兄弥太郎と弥太郎の妻あい子に相当な額の生活費を置いてこなければならなかった。だから彼女自身は帰りの旅費と、当座の金(きん)を持って出ただけである。ヨーロッパに着いたら、演奏会をすればいいから、と彼女自身も思っていたし、また兄たちもそれを期待していた。ところが、ヨーロッパに来て一年以上も経つというのに、演奏会一つできない。念願のザウワー教授に教えて貰えることになったものの、高額な謝礼金をこれからいったい何度払い続けられるであろう。バーデンに留まってザウワーのレッスンを受け続けるならば、久は帰りの旅費にも手を付けなければならない。
 おゆみ
おゆみ
幼少の頃にソルフェージュを、5歳でクラシックバレエを、8歳でピアノを、9歳でトランペットを学ぶ。大好きな音楽に身を捧げるためにも、ピアニストを目指していたものの、諸事情により作曲家、そして音楽学者へと進路変更をするも、40代で某音大の楽理科(音楽学)を目指すために精一杯勉強中。7月には某ピアノコンペティションの予選に出場するために、プーランクの3つの小品を勉強中。








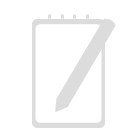
すごいね!おゆみさん、海老沢 敏とか磯山 雅というかもっとパワーあってすごい!がんばってね!勉強になりました!受験のことでなにかわからないことがあったら聞いてね!ちょっとしたことなら聞ける人いるので!びっくりぽんです!ありがとう❤
小川京子様、こんばんは。そしてはじめまして。
この度はコメントを寄せて頂きまして、有難うございます。
私は日本における西洋音楽の黎明期を研究の対象としています。私も勉強として「おゆみの音楽エッセイ」を連載させて頂いております。
今回は数少ない文献や資料を取り寄せたり、参考書籍を購入して調べ、拝読いたしました。
私は野本由紀夫先生の影響を受けていますが、海老沢敏先生、磯山雅先生は私も大変に尊敬しています。特に海老沢敏先生は日本におけるモーツァルトの研究の第一人者でもあり、私もモーツァルトに関しまして、大変に役に立たせて頂いております。
今回はピアニストの中村紘子先生の文献をメインの参考文献にしています。中村紘子先生には本当に感謝をしています。
私は音大受験まではまだ数年も先になりますが、今は基礎をしっかりと勉強をし、足固めをしています。
分からないことがございましたら、ぜひ質問をさせて頂きますので、そのときは宜しくお願い致します。