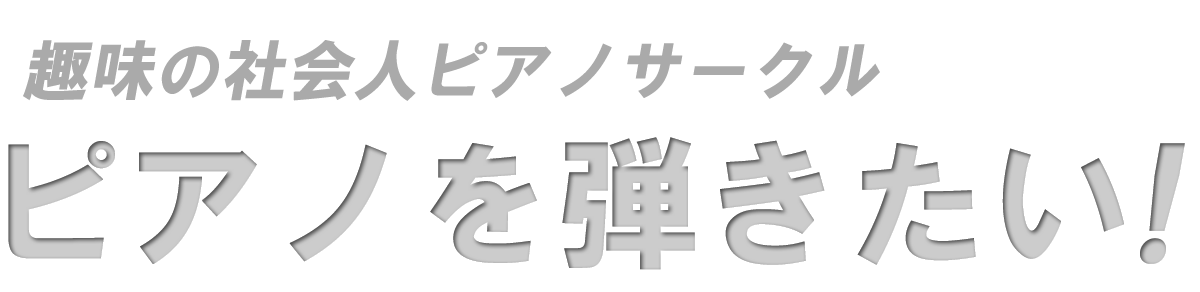ピアノ教室の月謝は、当初、週2回のレッスンで250円だったように思います。教室とはいっても近所の小さな長屋の一軒であり、ご近所なので多少、割り引いてくれたのかもしれません。同じ学校でピアノを習っている子供は、大抵、この先生のところに来ていましたが、それは概ね、裕福な家の娘らでした。世間一般が貧しいとはいえ、やはり、お金持ちはいたのです。
ピアノを習い始めたおかげで、私も5年生になる前に器楽クラブに入ることができました。当時のことですから合奏の中心はハーモニカと木琴であり、その他に打楽器やアコーデオンが混じります。その中で異彩を放ったのは、やはりピアノでした。そして、ピアノ演奏でクラブ専属のように振る舞っていたのは、一人の少女でした。彼女は私と同学年で、同じピアノ教室に通っていましたが、教室の中でもトップクラスのピアノ巧者でした。私は、合唱祭で彼女が伴奏した「荒城の月」の前奏の華麗さに啞然とした想いがあります。彼女は、なかなかの美少女でもあり、僕らマセ餓鬼の憧れの的でしたが、おまけに彼女の家は学校でも随一のお金持ちでした。一度、彼女の家に行く機会がありましたが、立派な応接室にピアノが置かれてありました。しかしですね、それは当然のようにアップライトピアノであって、当時は、プロでもない個人がグランドピアノを所有することなど想像にもおよばないことだったのです。
年に2度は発表会もありました。その内の一度は、中の島の大阪ガスのホールを借り切って催されたもので、当時としては贅沢なものでした。この時ばかりはと少女たちは、バレーの衣装かと見まごうばかりの白いドレスで着飾ります。学校での質素な身なりを見慣れた目には、別の国かと思うほどの華やかさに映り、童話の世界に紛れ込んだかのような錯覚に襲われました。エルメンライヒの「紡ぎ歌」などの定番曲が続く中で、いつの発表会でも必ず誰かが演奏して私の心に強い印象をもたらしたのは、デュランの「ワルツ」でした。全音のピースにも残るこの曲は、暗い会場をバックにした強い照明の中から急調子でホール全体に鳴り渡り、その中に短調の悲哀さを混じえた響きが、少年であった私の心に甘やかさを含んだ悲しみの感情を引き出しました。こうした経験が、後年に至っての私の精神に軟弱さを培った要因でもあったのだろうと、今になって思い当ります。