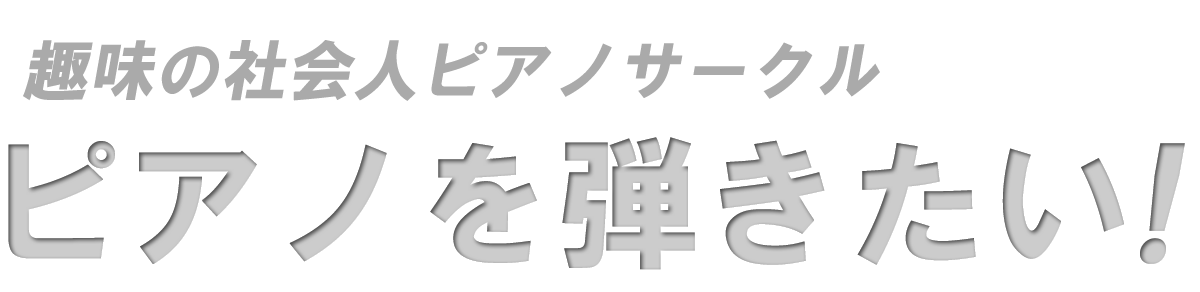これまでのピアノと自己との関わりについて思うことがあり、備忘録的に書きます。若干、鬱な話であることをあらかじめ御断りしておきます。
桐朋音大大学院生だったマリンバ演奏者の親戚にピアノを習い始めたのが小学校に上がる前くらいで、彼女が結婚で東京へ引っ越すことになり、中学校からは別の親戚に習うことになった。
やがて美術の方面に興味を持つようになったのでピアノは一度辞めたが、高校になって再開した。
はじめに習った親戚のつてで、常葉大学の20代の音楽講師に習ったが、こまか過ぎる指導でクラシックに拒絶反応が出るようになった。
そういう経緯で、クラシックピアノのレッスンは、あまり楽しかった記憶がない。
そもそも好きで弾いていた訳ではなく、音楽やってる親戚を食べさせるために大人の事情で利用されていただけだったなとやや被害妄想気味になった時もあった。
以降、ピアノも知人に譲り、音楽は聴くだけの趣味として四半世紀過ごしたが、練習会に出るようになり、発表会を機会にピアノを再開してみようと思った。
ショパンのバルカローレは、高校生の頃初めて自分で買った楽譜だった。
しかし弾く機会のないまま、先生や親が調達して来た楽譜を仕方なく弾かされるだけでレッスンは終始した。
夏にフランスへ旅行し、モン・サン・ミシェルから宿泊先のパリへ帰る経由地のレンヌ駅にあるピアノで、バッハのインヴェンジョンとショパンの幻想即興曲を弾き、聴いてくださったご婦人方に ‘Tre très bon’ の御言葉を頂いて、自発的にピアノに向き合える意識に切り替わることができた。
今回の発表会では、自分の意志で弾くことについて学ぶことができたと思う。
発表会は、変化に富んだ展開で、よくわからないけれどなるようになるという自由さがあった。
宗教狂いの母親はよく、神に祝福されているようなラッキーな「選ばれた人」を引き合いに出して、努力などしても無駄と諦めさせようとしてきた。
しかし、演奏は、いつでも一発勝負なので、うまくいけばそれはそれ、うまくいかなくてもそれはそれ、はじめから決まっていることなど何もない。
学生時代のクラシックピアノとそのレッスン体験は、親や教師の養分にされてしまった感じがするが、四半世紀を経て、人生折り返してきたところで、今度は自発的に取り組みたいと志を新たにした。
恵比寿にレンタルのドレスを返却しに行く途中日比谷線車内にて、20代のサラリーマンたちが、彼らの生涯年収およびライフスタイルの想像がつくような会話をしていた。生命を30年というまとまった期間切り売りして会社に捧げる人生。それは自分の意志でやっていることなのか、仕方なくやらされていることなのか。
ピアノという「悪魔」を通じて、四半世紀かけてようやく気づいたことは、親や教師の言うことなど聞いたところで、彼らの現状を継続させるための養分にしかならないということである。現在を犠牲にすることの対価は金銭では償いきれない。