
メンバー日記
 明治43年(1910年)、久は東京音楽学校の助教授に任命された。ピアノを始めて僅か9年、23歳の久は日本のピアノ界の未来を担って立つ者として、その名声、人気は人もうらやむ程のものとなった。
明治43年(1910年)、久は東京音楽学校の助教授に任命された。ピアノを始めて僅か9年、23歳の久は日本のピアノ界の未来を担って立つ者として、その名声、人気は人もうらやむ程のものとなった。
この年、7歳の少女が母親に手を引かれて、彼女の教えをもらいに門を叩いている。文豪で軍医の森鷗外の愛娘(まなむすめ)、茉莉(まり)である。後に彼女自身も作家となった森茉莉は、この7歳のときの思い出を、1984年当時の「週刊新潮」に連載だった「ドッキリチャンネル」でこう書いている。
「私には一つの恐ろしい思い出がある。久野久子(久のこと)という有名ピアニストがあった。私の父はその女(ひと)に私を習わせたいと思った。母が7歳の私を伴われてその女(ひと)を訪れ、ピアノを教えて遣(や)って戴(いただ)きたいと申し入れた。久野久子は天才であって、人柄もひどく変わっていた。束髪の前髪からはお化けのように髪の毛が下がっている。恐ろしい手付きで私を椅子につかせ、弾いてごらんなさいと命じたが私は恐ろしくて、碌(ろく)に弾くことも出来ない。母は恐る恐る、ご挨拶をし、私を伴れ帰り、父に報告した。私に大甘の父は無論、そこへ遣ろうとはしなかったがその後、久野久子は伊太利(イタリア)に行き、そこで向こうのピアニストの弾奏(だんそう)を聴き、自身のピアノに絶望した。そうして、ホテルの窓から飛び下りて死んだ。烈しい芸術家の死である。私はそのときの彼女の気持ちを思い、胸を打たれたことを、思い出す度に切なくなる。」
まず文中、伊太利に行き、というのは森茉莉の記憶違いであるが、いずれにせよ、恐らく彼女(森茉莉)は帰宅してから「怖かった、お化けのような先生だった」と最愛のパッパに語って聞かせ、そして鷗外は「よしよし、いい子だ。それなら行くな」とでも答えたのであろう。鷗外は22歳から26歳までの間、人生で最も多感な時期をベルリンで暮らした、という経歴のわりには、西洋音楽に対して関心の薄い人であった。ここで茉莉が我儘(わがまま)を言い出さずに、久のところに通い始めていたらどうなっていたのであろうか….
 ちょうど同じ頃、久野久のもとには中條(ちゅうじょう)ユリという丸顔の少女が熱心に稽古に通っていた。帝大卒業後、イギリスのケンブリッジ大学に長年留学していた親の影響で、ユリの家庭は極めてハイカラなものだった。夕方勤め先から帰宅すると、父は出迎える娘を西洋式に抱きキスをする。一家揃ってのディナー、日曜日にはイギリス式のハイ・ティを楽しみ、そして夜は暖炉の燃えるサロンに集まってユリのピアノに合わせて歌を歌ったり、といった中條家の日常は、当時の日本社会の中では珍しいものであったことだろう。
ちょうど同じ頃、久野久のもとには中條(ちゅうじょう)ユリという丸顔の少女が熱心に稽古に通っていた。帝大卒業後、イギリスのケンブリッジ大学に長年留学していた親の影響で、ユリの家庭は極めてハイカラなものだった。夕方勤め先から帰宅すると、父は出迎える娘を西洋式に抱きキスをする。一家揃ってのディナー、日曜日にはイギリス式のハイ・ティを楽しみ、そして夜は暖炉の燃えるサロンに集まってユリのピアノに合わせて歌を歌ったり、といった中條家の日常は、当時の日本社会の中では珍しいものであったことだろう。
中條ユリが15歳の冬、師匠である久野久が指をひょうそうにやられ、週2回の稽古が中断されることになった。久のひょうそうが完治するのには、それから4ヶ月もかかるのだが、その休みの間にこの多感で早熟な少女(中條ユリ)はそれまで没頭していたピアノから突然文学に目覚める。小説を書き始めたのである。この少女即ち後の宮本百合子は、この久野久との係わりあいをその長編小説「道標」の中で詳しく書いている。そこで久野久は、女主人公伸子(ユリ)のピアノ教師川辺みさ子として描かれているが、5年の長きにわたって師事した人のことを書いているだけに、その描写はまことに鮮明かつ具体的である。なかでも私を含め、ピアノを弾く人たちにとって、強い関心を持ってたのは、川辺みさ子のピアノ奏法についての描写である。
「伸子は、ピアノに向かって弾いているとき、よくその横についている川辺みさ子から、不意に手首のところをぐいとおしつけられて、急につぶされた手のひらの下でいくつものキイの音をいちどきに鳴らしてしまうことがあった。川辺みさ子の弾きかたは、キイの上においた両手の、手首はいつもさげて10の指をキイと直角に高くあげて弾らす方法だった。それは、どこかにむりがあって、むずかしかった。われ知らず弾いていると、いつの間にか手くびは動く腕からは自然な高さにもどってしまって、川辺みさ子の指さきで….いつもそれはきまって彼女の人差し指と中指とであったが、ぐぃときびしく低められるのだった。」(宮本百合子 道標第2部第2章4の第3段落)
明治以来、平成の今日に至るまで、日本のピアニズムの偏頗(へんぱ)な、「ハイ・フィンガー奏法」の具体的な例が、ここで実に鮮やかに描かれているのである。
久の奏法については、他にも多くの人が書き残しているが、そこでは久が常に指先のトラブルに悩ませていたことが出てくる。烈して練習を長時間にわたって行うあまり、久の指先は常に割れ、演奏中に鍵盤が血に染まることもしょっちゅうであったらしいが、それがあたたかも彼女の天才性を現す誇るべき偉大な出来事とでもいうように、多くの文献のなかで語られているのである。
そうやって考えてみると、久のようにしょっちゅう指先に怪我をしたり、ひょうそうにかかったりするのは、余程特異な体質でない限り、結局この甚だしく不自然な奏法をしてたためとしか考えられないことになる。つまり久の奏法は、ピアノを素手の指先を曲げて上から「ぶっ叩いて」いるのと変わりはなかったのである。 さて、ここに至って久の生活自体も、ようやく長年の貧乏暮らしから解放されるようになった。彼女の名声をしたって、東京の上流階級の子女たちが我先にと弟子入りを志願して押しかける。かつて京都に残って邦楽を学んでいた久の来し方行く末を案じ、「これからは洋楽だ」と方向転換を命じた兄弥太郎のカンは、まさに当たっていた。
さて、ここに至って久の生活自体も、ようやく長年の貧乏暮らしから解放されるようになった。彼女の名声をしたって、東京の上流階級の子女たちが我先にと弟子入りを志願して押しかける。かつて京都に残って邦楽を学んでいた久の来し方行く末を案じ、「これからは洋楽だ」と方向転換を命じた兄弥太郎のカンは、まさに当たっていた。
その弥太郎はその後帝大は卒業したものの定職には就かず、専(もっぱ)ら妹久の世話係、今日でいうマネージャー役を引き受けていたが、それは反面彼とその家族の生活の一切を久が支えることになった。加えて異母姉のあい子の一家も貧しく、久は結局のところ生涯この兄姉の面倒を見続けることになったのである。
(その5に続く。次回の執筆は、明年の1月2日頃になります。)
 おゆみ
おゆみ
40代にして音楽学者を志して、音大の楽理科に進学するために勉強中。来年1月の発表会に向けてショパンの「ポロネーズ第1番」を演奏するため、必死に練習に励みながら、日本における西洋音楽の黎明期の研究に情熱を注いでいる。








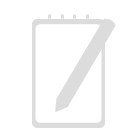
Leave a reply