
メンバー日記
 その頃久は、弥太郎のマネージメントで朝鮮と満州にも渡り、度々演奏も行っている。京城では定員1200名の会場に800名の入り、その内訳は5円券が300に3円券が500と、そうした記録を兄弥太郎は毛筆で克明に書き記している。京城の次は奉天、大連、しして旅順へと、弥太郎・久の旅は続くが、どこも700から800の入りであった。明治から大正にかけてのあの時代、情報網の限られ乏しかったあの時代のクラシック音楽の普及度から考えれば、今の3000から4000の大聴衆に匹敵する入りといえるだろう。
その頃久は、弥太郎のマネージメントで朝鮮と満州にも渡り、度々演奏も行っている。京城では定員1200名の会場に800名の入り、その内訳は5円券が300に3円券が500と、そうした記録を兄弥太郎は毛筆で克明に書き記している。京城の次は奉天、大連、しして旅順へと、弥太郎・久の旅は続くが、どこも700から800の入りであった。明治から大正にかけてのあの時代、情報網の限られ乏しかったあの時代のクラシック音楽の普及度から考えれば、今の3000から4000の大聴衆に匹敵する入りといえるだろう。
明治維新と共に始まった近代国家路線を試行錯誤しながらともかく突っ走ってきた日本は、大正時代に入るとその国家としての存在と主張が国際的にも認知されるようになってきた。特に大正3年(1914年)に勃発した第一次世界大戦は日本経済にかつてない活気と繁栄をもたらし、それが音楽の分野にも及んだ。そして、早くも世界の音楽興行師、マネージャーたちの関心を引き寄せることとなった。東京は「音楽市場」の一つになり始めたのである。
レコードが普及し始め、ピアノからハーモニカに至るまでの各種の楽器の製造が盛んになり、ジンバリスト、クライスラー、ハイフェッツといった当時のスーパースターたちがやって来た。更にオペラが上演し始める。帝劇(帝国劇場)、浅草オペラ、そして新しく設立された(大正2年)宝塚少女歌劇(現、宝塚歌劇団)などといったものの活動は日本の若い音楽界を刺激し、またその対象を広く大衆化した。明治に導入されて以来、一般大衆には全く無縁のものとされてきた西洋音楽が、ここに至ってようやく生活文化の様々な面において根付き始め、その響きももはやかつてほど奇異なものとは受け止められなくなってきた。こうした社会的背景のなかで、久の演奏活動もまた広がりを見せることが可能となったのである。 そんな久にとって、順風満帆を思わせる或る夜。大正4年(1915年)の1月、まだ空が明けていない早朝になって、通行人が黒っぽい布のかたまりのような物体が赤坂溜池の交差点近くの路上に打ち捨てられているのを見つけた。近寄ってみると、物体と思わせたのは人で、しかも女性であった。東部から出血していて意識もない。身元も不明である。ともかくも警察官が呼ばれ、その女性は築地(現、東京都中央区)の病院にかつぎ込まれた。
そんな久にとって、順風満帆を思わせる或る夜。大正4年(1915年)の1月、まだ空が明けていない早朝になって、通行人が黒っぽい布のかたまりのような物体が赤坂溜池の交差点近くの路上に打ち捨てられているのを見つけた。近寄ってみると、物体と思わせたのは人で、しかも女性であった。東部から出血していて意識もない。身元も不明である。ともかくも警察官が呼ばれ、その女性は築地(現、東京都中央区)の病院にかつぎ込まれた。
つまり事故が起きたのは、1月21日の深夜11時から11時半頃(報知新聞大正4年1月23日:「21日夜11半頃」説)である。久の交通事故は当時大騒ぎとなった。
本人が意識不明で身元が分からなかったため、昏睡状態の顔写真を大きく入れた尋ね人広告が1月23日の新聞各紙に掲載された。その後すぐに東京音楽学校助教授の久野久だと分かり、記録用の新聞印刷原版からその顔写真が削除されるなどとされた(これは、新聞の尋ね人広告に意識不明の久の顔写真を入れたのは、赤坂の歓楽街で働く一女性と間違われたためだったという。大正4年1月24日の報知新聞は見出しに、「大天才を害した償い/取扱上の遺憾なる事ども」と書き、次のように報じている。
「顔に(ママ)負傷し、且つ頭部に繃帯(ほうたい)(ママ)して相格変われる彼女の写真を麗々し掲載し縁なき人々にも不快の感を抱かしめ(た)は甚だ惨酷(ママ)の所為なりとの非難あり殊(こと)に警察官及び自動車側の婦人に対する観察が最初○○婦なるべしとの人格も無視したる推定に基づき総ての手心にて扱ひたる結果純潔たる処女に対してあるまじき陵辱を加へ露骨な身体検査を行ひしやの風説(略)」(報知新聞大正4年1月24日)
肋骨も何本か折れていた。すぐに手術が行われ、とりあえず一命はとりとめたものの、久の病状は極めて重かった。結局久はその病院に3ヶ月近くも入院することになる。
この交通事故以来、久の言動は明らかにおかしくなった、と、彼女に親しかった人々は言う。久はそもそも上方弁なまりが強く、そこに外国流のやや大袈裟な身振りや感嘆詞が加わって、親しい者同士の会話では極めて荒っぽくなるのが常であった。彼女自身もそれを意識しており、努めて柔らかく話そうとしていたのだが、この事故以来彼女は感情のコントロールの失ったかのようだった。しゃべり方だけではない。情緒が不安定になり、愚痴をこぼしたのかと思うと、今度は自分の天才性について語りだす。眼をギラギラとさせながら早口で喋りまくり、他人の言葉が入り込む余地もない。現代でいえば、高次脳機能障害と診断されていたであろう。そして空気の読めないほどの症状であったのではないだろうか。もっとも、例え脳に異常がなかったとしても、こうした状況に追い込まれたのなら、誰だって情緒不安定になるであろう。足の不自由さに加えてこの大事故、果たして自分は、元の身体に回復するだろうか?再びピアノが弾けるようになるのだろうか?彼女の稼ぎを頼りにしている兄、姉、甥や姪の顔が目の前にちらつく。このとき久は27歳であった。 この間に東京音楽学校では、久の後輩である小倉末子が大正5年(1916年)4月23日にアメリカから帰国、すぐに東京音楽学校の講師に就任、1年後の大正6年(1917年)4月、講師から教授となる。助教授を飛び越し教授となるのは極めて異例であった。
この間に東京音楽学校では、久の後輩である小倉末子が大正5年(1916年)4月23日にアメリカから帰国、すぐに東京音楽学校の講師に就任、1年後の大正6年(1917年)4月、講師から教授となる。助教授を飛び越し教授となるのは極めて異例であった。
ここで小倉末子について少々触れておきたい。末子は明治24年(1891年)2月、岐阜県大垣市で生まれ、東京音楽学校を中退し、ベルリン王立音楽院(現、国立ベルリン芸術大学)でハインリッヒ・バルトに師事。アメリカのメトロポリタン音楽学校教授を経て、前述の東京音楽学校教授となる。
末子はベルリン、シカゴ、ニュー・ヨークなど、海外で日本人女性として演奏家と認められた。他にソプラノの三浦環がいるが、彼女は声楽家なので、ここでは割愛する。
日本人女性初のゴルファーでもあった。兄は貿易商で財を成し。当時日本人で唯一六甲山に別荘を持っていた人物であった。また兄の妻がドイツ人で、彼女が末子にピアノの手ほどきをしたといわれている。
末子と久とは対照的で、私生活では時代の最先端を歩んでいた。久は常に和服姿であったが、末子は洋装で暮らしていた。大正から和服姿になったが、これは軍国主義に突入したためでだと考えられる。
そんな末子だが、昭和19年(1944年)9月25日に逝去。享年54歳という早い死であった。
 話を久に戻して、久は大正6年(1917年)8月に東京音楽学校の教授に昇進、その翌年に初めてベートーヴェンの作品だけのよるリサイタルを開催する。「ベートーヴェンの午后」と名付けられたこの独奏会はまた、久の交通事故からの完全復帰を世に知らしむる記念演奏会でもあった。作家・江馬修はそのときの彼女の演奏を聴き、殊に「アッパショナータ(熱情ソナタ)」に非常に感動した。
話を久に戻して、久は大正6年(1917年)8月に東京音楽学校の教授に昇進、その翌年に初めてベートーヴェンの作品だけのよるリサイタルを開催する。「ベートーヴェンの午后」と名付けられたこの独奏会はまた、久の交通事故からの完全復帰を世に知らしむる記念演奏会でもあった。作家・江馬修はそのときの彼女の演奏を聴き、殊に「アッパショナータ(熱情ソナタ)」に非常に感動した。
「曲の解釈もあまり確かだとは思はれなかつた。しかしそこには天才の直観が閃(ひらめ)いてゐた。もとより曲の偉大な情熱を支配するだけの力はなかつた。しかもそれには猶(なお)演奏者の美しい輝く情熱と讃嘆すべき力があつた。そして倒れるまで弾きつづけようとする必死の努力が寧(むし)ろあの人を痛々しく思はせたー」
久の演奏のあり方が、そしてその彼女を取り囲む讃美者たちの受け止め方が目の前に浮かぶようではないか。江馬はその後もなく久と個人的に親しくなり、勝気で負けん気の孤独な久が本音を吐露したほとんど唯一の友人となる。久から江馬に宛てられた手紙は100通近くにのぼるが、そのどれをとっても世間でいわれている久とは違う。気弱で悩みに溢(あふ)れた優しい一人の女性の姿が浮かび上がる。
さて、この復帰記念演奏会は大成功に終わり、ピアニスト、特に「べートーヴェンの大家」としていまや久野久の地位は揺るぎないものとなった。そして久自身も、交通事故でいったんは絶望視した自分の未来に大きな希望を取り戻すようになる。残るは世界制覇だけだ、いつの間にやらそういうそそのかしを久の周囲でささやくものも出てきた。あなたは今や日本の久野久ではなく、世界の久野久である。あなたの情熱、あなたの芸術性、あなたのベートーヴェンへの深い共感をもって、本場の人々を驚愕(きょうがく)させておやりなさい、と。
久が「自分のベートーヴェンでウィーンを征服してくる」とか「これからの自分こそ天才を発揮するのである」とか喋ったという噂には尾ひれや羽がつき、一周して彼女の耳に入る頃には更に大きく膨らんだ。そしてそれらはプレッシャーとなって久の心を動揺させ、自信と不安の間を迷わせた。
「私は西洋ゆきは臨みませぬ。西洋へ行かずに十分ニギレル自信と、このまま日本にゐたい我が儘があります。けれど二年三年五年自由な時間がほしいのです。さうしないと今のあはれさのつらさを抜けられませんー」。江馬への手紙の一節である。
この大正7年の「ベートーヴェンの午后」から、渡欧する大正12年(1923年)までの約5年間というものは、久の日本における絶頂期であったのとは裏腹に、その不安焦燥も募った時期であった。
久は自分の音楽における情熱、狂気は、音楽の本当の姿を知らないことからくる不安と、そしてそこから目を背けるためのものであることを本能的に感じ取っていた。彼女と音楽との出逢い、関わりあいには何一つ豊かなもの幸せなものではなく、あるのは不安とつらさばかりであった。そして音楽に身を打ち込めば打ち込む程にその不安は広がり、彼女から音楽はますます遠く隔たって行くのを彼女は知っていた。そんな自分が本場に行って、音楽の真実の姿に真っ向から向かい合ったとき、自分はそこに何も見出すのだろう?彼女は直観的に自分の破滅を予感し、怯えた。しかしそのことは誰にも知られたくない。彼女は、自分が世間が誉めそやすように「天才」であること、「偉大な芸術家」であることを信じることに没頭した。
大正12年春、久は2回目の「ベートーヴェンの午后」を開催した。渡欧記念、フェアウェル・コンサートと銘打ったこのリサイタルは文字通り彼女の「告別演奏会」となる。プログラムは「告別ソナタ」、「ハンマー・クラヴィーアーソナタ」、「作品110」、「作品111」であった。これはもう一つの教壇であった日本女子大学校の櫻楓会の研究発表の場でもあった。そして同年4月12日、久はついにヨーロッパに向け東京駅を出発する。これは留学という名目で、実は左遷であった可能性が高かったという。
(その6に続く)
 おゆみ
おゆみ
明けましておめでとうございます。
「おゆみの音楽エッセイ」は私おゆみがクラシック音楽を中心に今までに見てきたこと、聞いてきたものなど、五感で感じたことをエッセイにして、皆様にお届けしたいと考えています。
精一杯執筆を致しますので、本年も宜しくお願い致します。








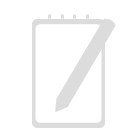
Leave a reply